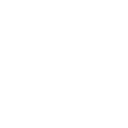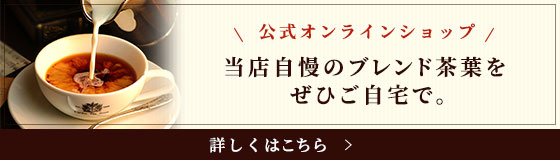日本のミルクティーは、季節感のあるものとして定着しています。
紅茶屋、それもミルクティーを専門とする我々からすると、できればオールシーズン普及してほしいのですが……。
なぜ、日本ではミルクティーがなかなか定着しないのでしょうか?今回はその理由を考えつつ、日本でミルクティーを広める方法について考えていきます。
イギリスの紅茶は「おいしさ」命

まずは、ミルクティー大国のイギリスから、ミルクティーが定着した背景を学んでみましょう。
イギリスでは、各メーカーが”おいしいミルクティー”を送り出そうと、競い合って追求しています。おいしい紅茶に、これまたおいしいミルクをたっぷり入れて味わうスタイルです。おいしいミルクと紅茶の組み合わせが人気なこともあり、イギリスのスーパーにはミルクティー用の茶葉がぎっちりと置いてあります。
なぜ、こんなにもミルクティーが人気なのか。
色々と理由があったりします。
ストレートで飲むのが難しい茶葉もあった
イギリスに紅茶が入ってきた当初は、薬用として飲まれていました。しかし、中にはストレートで飲むのが難しい茶葉もあった様子。
というのも、当時は紅茶の味を整えるために、茶葉をブレンドする考え方がなかったのです。
現代でも、ダージリンのような一部の紅茶は、ブレンドせずそのまま飲むケースもあります。
ただ、アッサムのように渋みが強い紅茶を、ブレンドなしで飲むのには厳しいものがあったのです。
薬用と割り切れば、ガマンできたかもしれませんが。
そこで考え出された方法が、イギリスの特産品であるミルクを入れること。
渋みや雑味を中和し、味を良くして飲むことができました。
もっとも、当時の紅茶と牛乳は高級品……。それらを組み合わせて飲めること自体が、ステイタスシンボルだったのかもしれません。
色の悪さを隠すミルク

もうひとつの理由が、色を隠すため。
というのも、イギリスの主要都市では、硬水で紅茶を淹れます。味は濃く出るのですが、色が真っ黒になるんです。イギリスで紅茶を「ブラックティー」と呼ぶのも、これが理由。
そんな紅茶を見せてはならぬということで、先にミルクを入れてから、紅茶を注ぐようになりました。これが世にいう、ミルクインファーストの由来だったり。
温度を下げて陶磁器を守る
最後の理由が、食器を守るため。当時、上流階級の使っていたティーウェアは、もっぱら中国から輸入した陶磁器でした。しかし、この陶磁器に直接熱い紅茶を注ぐと、割れてしまうことがあったのです。
1度壊れたら、手に入れる手段は輸入しかありません。おそらく、現在では考えられないほど値が張ったでしょう。
そこで考案されたのが、先にミルクを注いで、紅茶の温度を下げる方法でした。イギリスのミルクティーに、冷たいミルクを使うのは、こういった背景があったんですね。
コラム:ミルクティーは猫舌に優しい
紅茶にミルクを入れるのは、温度が下がって飲みやすくなるから、という理由もあります。紅茶を淹れたタイミングでは、温度が80~90℃。アツアツの状態では、イギリス人はとても飲めません。そこで冷たいミルクを入れて、ちょうどいい(日本人にとってはぬるい)温度にします。
実は、アツアツのものを飲んだり食べたりできる人種は、日本人くらいです。温かいものはアツアツ、冷たいものはキンキン……。海外からは、この食習慣がクレイジーだといわれているとか。
日本は紅茶を「ブランド」で見る

さて、一方の我が国、日本。日本で紅茶といえば、どっちかというとストレートティー派が多くなっています。
なぜ、日本ではストレート優勢なのか?考えてみました。
「産地」を重く見る文化
考えられる理由としては、日本のお茶文化で「産地」が重要視されていることがあります。
味や香りより産地、というと誤解を招きそうですが……。実態としては、「〇〇産のお茶なら優れているに違いない」という、ある種の信用やブランド力があるものと考えられます。
歴史をひもとくと、室町時代には「闘茶」とよばれる、産地を言い当てるゲームが行われていた様子。産地が重要視される日本だからこそ、生まれた遊びなのでしょうか。
「御用達」は日本でも強い
イギリスの紅茶メーカーには、「王室御用達」と呼ばれるものがあります。同じように、日本茶にも「将軍御用達」なる称号があるんです。
たとえば江戸時代は、将軍家が静岡茶の清算に注力していたこともあり、静岡茶(足久保茶など)がプッシュされていました。
イギリスと違うのは、各大名がそれぞれ推すお茶どころがあったこと。ビッグネーム(大名を英訳したらこうなる)の後ろ盾を得られたお茶どころが、その知名度を伸ばしていくことになります。
有名どころでいうと、「宇治抹茶」は室町時代の足利家が推していたお茶どころです。当時は京都に幕府があったので、いわゆる「お膝元」だったのでしょう。
そんなお茶に「手を加えて」飲もうものなら、何かしら言われてもおかしくなかったのかもしれません。過激な大名ならば、ちょっと危ないことになったりしないでしょうか?武士のプライドがすべての時代ですし。
これからの紅茶商戦

上記のような経緯もあり、日本の紅茶は素材そのままを味わうのが普通になっています。
逆に言えば、ミルクティーが浸透する(物理的にではない)土壌が育っていません。
茶葉から紅茶を淹れて、ミルクティーを作る文化を広めるには、どうしても「紅茶そのもののおいしさ」に目を向けてもらう必要があると考えます。
ペットボトル紅茶は人気
ご存じの通り、ペットボトル紅茶は、茶葉よりよく売れています。実際の数字を見てみると、ペットボトルの年間売上額は2219億円(2023年)という大きな産業でした。
茶葉の売上に関するデータはないものの、さすがに2千億円には届かないでしょう。
この差ができた大きな理由は、ペットボトル紅茶は「おいしさ」に注目されているため。販売戦略の一環として「〇〇茶葉使用」と言われることはあるものの、見ている方は少ないでしょう。
「おいしさ」で勝負する必要性

日本でミルクティー用の茶葉を売ろうとしたら、紅茶メーカーだけでなく、ペットボトル紅茶を販売する飲料メーカーが対抗馬になります。
ペットボトル紅茶中心の消費者層をいかに取り込めるかが、キーになるでしょう。
まずは、「ミルクティー用の茶葉」という概念と、茶葉から作るミルクティーのおいしさを知ってもらうこと。
産地とおいしさがリンクしている日本では、ブレンドという考え方があまり浸透していないので、ここが一番の鬼門です。
その上で、ミルクティーに適した牛乳や茶葉などの競争が始まれば、ミルクティー党も増えてくるのではないでしょうか?
あわよくば、ミルクティーを楽しむ人のため「ミルクティー用の牛乳」ができれば、と考えています。イギリスの濃厚な牛乳の風味があれば、ミルクティーの人気はより高まるかもしれません。
願わくば、ミルクティーが「季節の風物詩」でなくなってくれればよいと思います。年中おいしいものですから。
ミルクティーのおいしさを知ってもらいたい

ミルクティーへの愛そのままに、日本でミルクティーを流行らせる方法を考えてみました。
とはいえ、歴史というものは相当に重い様子。イギリスでミルクティーが広まったように、日本では抹茶や煎茶が広まっていましたから……。
逆に言えば、ミルクティーが愛されるベースはできています。
ここから消費者の目線をとらえた商品開発をしていけば、日本にもミルクティー文化が根付いてくれるでしょう。