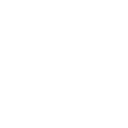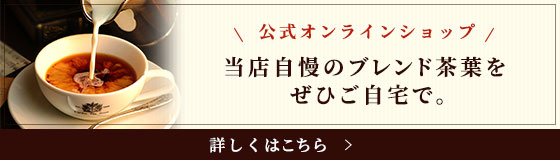11月1日は「紅茶の日」。今から約200年前、日本人が初めて紅茶を飲んだ日として、日本紅茶協会により制定された記念日です。
初めて紅茶を飲んだ日本人、と聞くと、とても名誉なことに聞こえるかもしれません。実際、当時の日本ではまず考えられない名誉だと思います。
しかし、その裏側には、多くの苦難があったのです。
今回は「紅茶の日」のお話と題しまして、日本で初めて紅茶を飲んだ人「大黒屋光太夫」の足取りを追っていきましょう。
ロシアに漂流した日本人

▲光太夫が出航した白子港。現在も漁港として使われている
ことの始まりは、1782年(このとき31歳)でした。地元である白子(三重県鈴鹿市の南若松あたり)から江戸へ、出航した光太夫は、嵐に巻き込まれ漂流する羽目になります。
このとき乗っていた船員は、光太夫を含む17人と、猫1匹。光太夫は船に乗る際、節用集(辞書)・浄瑠璃本(人形劇の台本)・尺八に加え、猫を必ず連れて行ったそうです。もしかすると、ネズミ捕りに役立ったのかもしれません。
しかし、出航からわずか4日で難破し、8カ月以上を漂流することになります。ほうぼうの体でたどり着いた陸地は、ロシア領の小さな島・アムチトカでした。
帰国の夢かなわず

▲白子漁港付近にある、白子港緑地の猫。現在も猫が多いことで有名。光太夫の愛猫も、カムチャッカ半島まで渡ったという
なんとか現地の人に受け入れてもらい、生活を始めたものの、江戸幕府からは帰国の許可が下りません。当時は鎖国の時代真っ只中であり、国外に出た日本人にも、帰国の許可が下りなかったのです。
途方に暮れた光太夫一行でしたが、一縷の望みをかけてロシアの首都・サンクトペテルブルグを目指します。この時点で、漂流から4年が経過していました。
謁見と初めてのミルクティー

▲ロシア・日本で描かれたエカテリーナ2世の肖像。右側は聴取によるものながら、絵画と似ている部分が多く見受けられる
左)ウィーン美術史博物館蔵「エカテリーナ2世(キャサリン)」。アレクサンドル・ロスランの作 ©Public Domain
(右)「北槎聞略 器材・装身具等」。蘭学者・桂川甫周が聴取した内容を参考に描いたもの。©国会図書館デジタルアーカイブ
光太夫一行の旅は、過酷なものでした。なにせ、カムチャッカ半島の東にある島から、シベリアを丸ごと越えようというのですから。
極寒の中、仲間を失いながらの、過酷な旅路。4年かけて、ようやくサンクトペテルブルグに辿りつきました。光太夫が申し出たエカテリーナ2世との謁見は、速やかに受託されます。
光太夫一行の過酷な旅路を想ったエカテリーナ2世は、幾度かの謁見の後、帰国を許可します。当時のロシアは、日本と国交を結ぶきっかけを探していたのも、光太夫にとっては幸運でした。
こうして、光太夫達は日本に帰ることができたのです。
11月1日のお茶会

光太夫達が日本へ帰る直前、1791年11月のこと。生き残った光太夫一行3名は、エカテリーナ2世のお茶会に呼ばれることとなります。
光太夫達が紅茶(ティー・ウィズ・ミルク)を楽しんだのは、このタイミングです。果てしない旅路の末、たどり着いたミルクティーのおいしさは、きっと格別だったことでしょう。
また、この出来事から11月1日は、日本紅茶協会により「紅茶の日」に指定されています。
しかしながら、お茶会に関する細かい日取りは、記録として残っていないともされており……。資料によっては、お茶会の有無を疑う声もあるほどです。
光太夫たちのその後

▲光太夫と磯吉。帰国した際は洋装だったという
Anonymous Japanese painter 1792, Public domain, via Wikimedia Commons
1792年、北海道・根室に帰り着いた光太夫たちでしたが、実際に帰国が許可されたのは翌年・1793年のこと。日本とロシア間の交渉がこじれ、結局9か月間待つ羽目になりました。
17人と1匹の仲間のうち、帰国できたのはわずか3名。長い旅の中で、仲間たちは亡くなったり、立場の弱さに耐えかねてロシアに帰化を余儀なくされたりしていました。あろうことか、日本にたどり着いた3人のうち1人は、根室で命を落とすことになります。
その後はロシアとの交渉材料として、半ば幽閉のような形で、江戸への在住を許可されることに。78歳で亡くなるまで、その体験を様々な人に語り継いだようです。
紅茶の日と大黒屋光太夫

▲三重県鈴鹿市にある、大黒屋光太夫記念館。入口には光太夫の像が建てられている
毎年11月1日、紅茶の日。紅茶メーカーがそろってキャンペーンを開催する、華やかなイベントとなっています。
そんな華やかさとは裏腹に、日本人が最初の紅茶を口にするまでは、10年近くに及ぶ過酷な旅路がありました。
11月のはじめ、紅茶の日は、ぜひ光太夫のことを思い出してみてください。映画『おろしや国酔夢譚』をはじめとする、光太夫を題材とした物語を見るのもよいでしょう。
極寒の地で、故国に帰りたいと願った、彼の勇気と覚悟を垣間見られるかもしれません。